「英語以外の外国語も学ぼうかな」と思ったことありませんか?
私は南米に6年間住んでいたこともあり、英語、スペイン語、ラテン語、ロマンス諸語などの多言語学習に取り組んでいます。そこで今回は、「多言語を学んで良かったメリットとデメリット」についてご紹介します。多言語学習を始める何か参考になれば幸いです。
多様な文化を知ることができる
1つ目のメリットは、多様な文化を知ることができることです。
「言語」を学ぶことは「文化」を学ぶことでもあります。なぜなら、異なる言語を持つ人と会話をするには、相手の言葉だけではなく、相手の(国や地域の)文化・習慣・マナーを知る必要があるからです。言語と文化は表裏一体です。
例えば、海外の有名なマナー違反に「鼻をすする」という行為があります。私も南米に住んでいる時にうっかり鼻をすすってしまい、「何で鼻をかまないの?」と凄い嫌な顔で指摘されたことがあります。今でも覚えている苦い思い出です。
ことわざの「郷に入っては郷に従え」が分かりやすいたとえだと思います。いくら語学が堪能だとしても、鼻をすすりながら話していたら、その時点で論外なわけです。言葉が話せるかどうか以前の問題です。
方言や話し方の違いがあるように、慣習やしきたりにも違いがあります。異なる言語を学んで誰かとコミュニケーションすることで、さまざまな文化を知ることができます。さらに言えば、多様な考え方や視点を持つことにつながり、寛容さや心の余裕なども生まれるかもしれません。
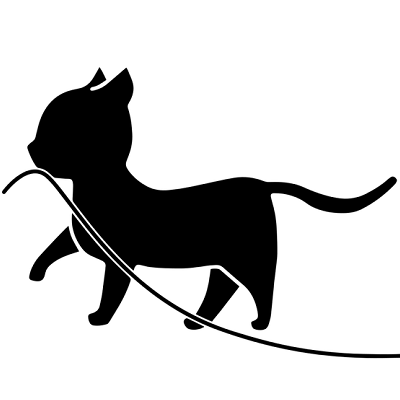
多言語学習は言語的なメリットだけでなく、人生にとっても大きなメリットがあると思います。
英語の語彙力が向上する
2つ目のメリットは、英語の語彙力が向上することです。
例えば、英語で「洪水」というとfloodが一般的ですが、inundationという少し難しい言い方もあります。inundationは「氾濫(はんらん)、浸水、洪水」などの意味があり、15世紀頃にラテン語から英語に伝わりました。そのため、ラテン系の言語では、洪水を意味する言葉として一般的に使われています。
英語:flood, inundation*難しめ
ラテン語:inundatio
イタリア語:inondazione
フランス語:inondation
スペイン語:inundación
ポルトガル語:inundação
このようなケースは、同じ言語グループの外国語を学ぶ際によく起こります。英語では英検1級以上・TOEIC900以上の難しい単語も、そのほかのヨーロッパ言語ではそこまで難しくないこともあります。そのため、多言語を学ぶことで、英語の語彙力の向上も期待できます。
ほかの言語とどのくらい同じ単語が使われているかのことを、言語学では語彙の共通度(lexical similarity)と呼んでいます。例えば、英語はドイツ語と約50%、フランス語とは約30%の単語が共通していると言われています。
参照 英語の歴史を簡単に振り返る
参照 英語の語彙に影響を与えた外国語
ほかの言語の意味が推測できる
3つ目のメリットは、ほかの言語の意味が推測できることです。
これは語学的なメリットです。多くの言語にはつながりがあるので、知らない単語があっても、何となく意味が予測できる場合があります。先ほど紹介したinundation(洪水)も1例ですね。
別の言語でも意思疎通が出来ることを、言語学では相互理解可能性(mutual intelligibility)と呼んでいます。例えば、スペイン語が話せると、イタリア語やポルトガル語も半分以上は理解可能です。ほかにも、英語はスコットランド語と、ドイツ語はオランダ語と、お互いに意思疎通が可能だといわれています。これらの言語は、お互いに同じ言語だったため、現在でも文法や語彙に多くの共通点があるからです。
参考 スペイン語の歴史を振り返る
参考 ドイツ語の歴史を簡単に振り返る
ヨーロッパ言語の多くは「インド・ヨーロッパ祖語」という同一の言語から枝分かれしたので、このような似ている単語が沢山あります。特に、英語は外国語から大きな影響を受けて来たため、元からあった本来語(native word)は約20~30%しかありません。多くの研究では、英単語の50%以上はラテン語やフランス語に由来していると言われています。
ほかの言語の意味が推測できるメリットは、長文読解で役立ちます。ニュースでも小説でも、長文になるほど知らない単語も増えるので、意味を推測しながら読み進めることが多くなってきます。そのような場合でも、ほかの言語の知識から意味を理解できることがあります。
日本語の場合でも、中国語の意味がなんとなくわかる時ってありますよね。ただ、書き言葉という限定はありますし、「日本語と中国語で意味が違う漢字・漢語」には注意が必要ですが。
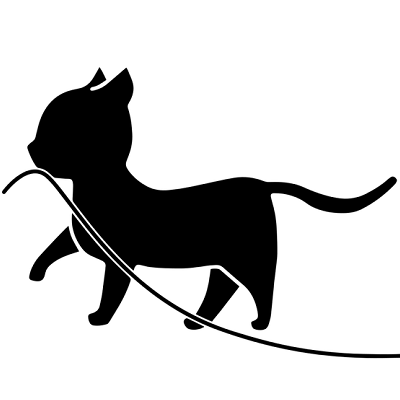
どの言語にもつながりがあるので、相乗効果で語学力をアップすることができます。
ボキャブラリーが増える
4つ目のメリットは、ボキャブラリーが増えることです。
純粋に日本語の語彙力が上がるという利点です。特に、カタカナ語や外来語に詳しくなります。語彙の幅が広がることで、豊かな表現にもつながります。私もこのサイトで、ドイツ語、オランダ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語などの外来語についてまとめていますが、自分でまとめていて勉強になるなと思うことが多々あります。
そのほかのメリット
多言語を学ぶことは、そのほかにも以下のようなメリットがあります。
英語に飽きた時の息抜きになる
人間は同じことを繰り返すと飽きてしまいます。脳が慣れてしまい、以前ほど刺激を感じなくなるためです。英語と違う言語を短時間でも学ぶことで、ゲームなどで遊んで過ごすより、有意義な息抜きになるかもしれません。
英語+1でより貴重な人材になれる
英語は2020年から小学校で必修化されました。そのため、英語を話す人はこれから更に増加することが見込まれます。必修化された英語だけでなく、もう1つの外国語を話せることで、より貴重な人材になることが出来るかもしれません。ひいては、キャリアアップにつながるかもしれません。
そのほかのメリット一覧
そのほかの多言語を学ぶメリットを一覧でまとめました。
- 世界が広がる。
- 視野が広がる
- 単純にかっこいい。
- 友達が増える。
- 趣味が増える。
- 知識が増える。
- 脳が発達する。
- マルチタスクが向上する。
- 日本語の意味を再確認することで日本語力が向上する。
- 多角的な視点で英語の学習が出来る。
- 周りが知らない言語で悪口が言える。
あくまで可能性に過ぎず、絶対にこうなる!とは断言できませんが、これらの可能性が考えられます。一覧で紹介したメリットの詳細については、また機会があれば追記したいと思います。
多言語学習のデメリットは?
多言語学習はデメリットが全くない、というわけではありません。
1つ目のデメリットは、労力がかかることです。言語は1週間や1か月で簡単に習得できるわけではありません。ある程度話せるようになったとしても、語学力を維持するだけで、時間や労力が必要です。学んでいる言語の数が多いほど、維持に必要な時間も累乗で多くなってしまいます。
2つ目のデメリットは、違う言語が混ざることです。言語学ではコードスイッチング(code switching)と呼ばれています。

私もスペイン語と英語の単語が混ざってしまうことがあります。例えば「会話」を意味する英語のconversation(カンバセーション)とスペイン語のconversación(コンベルサシオン)は、スペルはほとんど同じですが発音は異なります。似ている単語は覚えやすいという長所がありますが、意味や発音が混ざってしまうという短所もあります。
3つ目のデメリットは、AI翻訳の発展です。AI翻訳の精度は、年々飛躍的に向上しています。これは日本語と外国語というよりかは、英語とその他の言語、もしくは同じ語族の言語で顕著です。いつかは分かりませんが、人間が翻訳しなくても良い時代は訪れると思います。
とはいえ、言葉が人と人とをつなぐ存在であり続けるのなら、人間が多言語を話す意義や価値も、私はあり続けると思います。
まとめ
今回は「多言語を学んで良かったこと・悪かったこと」についてご紹介しました。
多言語を学ぶと、①多様な文化を知ることができる、②英語の語彙力が向上する、③ほかの言語の意味が推測できる、④ボキャブラリーが増える、というメリットがあります。
言語を学ぶことは文化を学ぶことです。なぜなら、誰かと会話をするには、相手の文化や習慣を知る必要があるからです。さまざまな言語を学んで誰かと話すことで、多様な文化や考え方を知り、理解することにつながります。また、多言語学習は英語能力や総合的な語学力の向上につながります。多言語学習はきっと新しい世界が広がるキッカケになると思います。
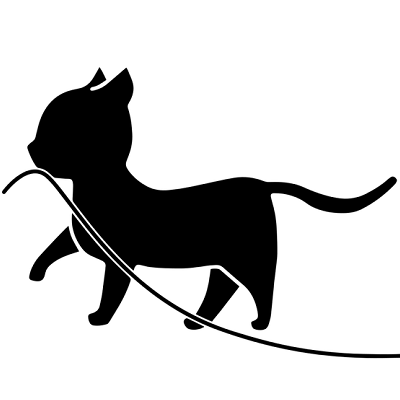
この記事が皆さんにとって多言語学習を始める、もしくは多言語学習を続けるキッカケに僅かでもなったなら嬉しい限りです。




